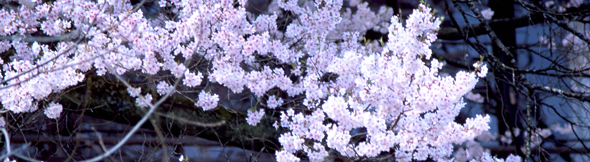
新しい職場に移って10日あまり。
今までとは全く畑違いの職場ですが、前から関わりたかった教育関連の仕事なので、刺激的な日々を過ごしています。
そして、3.11東日本大震災から1ヶ月。
物理的な揺れも大きかったし、未だに余震が続いています。
しかし、それにもまして、思考の揺れもとても大きかったような気がします。
今まで「こうだ」と思い込んでた価値観が、がらんがらんと根底から崩れ去り、あらゆる角度から見直されざるを得ないくらいの精神的な大地震でもありました。
それでも変わらず巡ってくるものがあります。
それは、大自然の営み。
いつまでも寒い気候でしたが、季節は巡り、やっと暖かくなってきました。

この時期が来ると、うきうきしてきます。
あちらこちらで花が咲き、チョウが舞い、暖かい南風が吹き始めます。
その中でも、最も関心を寄せるのが「桜」
桜の花を見るたびに、
桜の香りを感じるたびに、
そこに立ち止まって、
その美しさと儚さを目と心に焼き付けています。
花をつけない、春以外の季節は、とくに見向きもされない桜に、どうしてこんなに想いを募らせるのかとふと思った時に、一冊の本を思い出しました。
ベストセラーともなった藤原正彦著『国家の品格』です。
そこから少し引用してみます。
桜の木なんて、毛虫はつきやすいし、むやみに太いうえにねじれていて、肌はがさがさしているし、花でも咲かなければ引っこ抜きたくなるような木です。しかし日本人は、桜の花が咲くこの三、四日に命をかけて潔く散っていく桜の花に、人生を投影し、そこに他の花とは別格の美しさを見出している。だからこそ桜をことのほか大事にし、「花は桜木、人は武士」とまで持ち上げ、ついには国花にまでしたのです。
桜の花の時期になると、みながうきうきします。桜前線が南から上がってくると、もう吉野は満開かな、高遠や小田原はどうだろう、千鳥ヶ淵や井の頭公園は来週かな、弘前の桜はいつになるだろなどと、みな自分の知っている桜の名所が気になり出す。桜前線が地元に至ると、今度は天候を心配します。天候を心配するのは、花見の幹事だけではありません。桜は人生そのものの象徴だから、誰もが気になって仕方ないのです。
アメリカ・ワシントンのポトマック川沿いにも荒川堤持って行った美しい桜が咲きます。日本の桜より美しいかもしれない。しかし、アメリカ人にとってそれは「オー・ワンダフル」「オー・ビューティフル」と眺める対象に過ぎない。そこに儚い人生を投影しつつ、美しさに長嘆息ようなヒマ人はいません。
日本語には「もののあわれ」という言葉があります。
前後しますが、同書からもう少し引用してみます。

『平家物語』の中に、武士道の典型として新渡戸稲造の『武士道』の中でも引用される有名な場面があります。一の谷の合戦の際、熊谷直実(くまがいなおざね)が敵の平家の武将を捕まえた。殺そうと思って顔を見ると、まだ若い。十五歳の平敦盛(たいらのあつもり)だった。
自分の息子ぐらいの年である若者を殺していいものかどうか。熊谷直実は思わず逡巡するわけですが、さすが平敦盛は「首を討て」と直実に命令します。直実はしかたなく首を討つ。その後手にかけてしまった若者を悼んで、直実は出家してしまう。
このような敗者、弱者への共感の涙。これが日本の無常観にはある。お能の「敦盛」が今でも延々と演じられているのは、こういう無常観、武士道でいう惻隠(そくいん)に近いものが今も日本人の心の中に流れていて、心を揺さぶられるからでしょう。
この無常観はさらに抽象化されて、「もののあわれ」という情緒になりました。日本の中世文学の多くが、これに貫かれています。すなわち人間の儚さや、悠久の自然の中で移ろいゆくものに美を発見してしまう感性です。これは大変に独特な感性です。
ものが朽ち果てていく姿を目にすれば誰でもこれを嘆きます。無論、欧米人でもそうです。しかし、日本人の場合、その儚いものに美を感ずる。日本文学者のドナルド・キーン氏によると、これは日本人特有の感性だそうです。儚く消えゆくものの中にするら、美的情緒を見出してしまう。
たとえば、桜が3ヶ月も4ヶ月も咲き続けたら、ここまで桜の花に惹かれたかなと思うと、そうではないでしょうね。
儚く散っていくその姿に、自分の人生を重ね合わせ、移りゆく四季に生きていることを実感しているのでしょう。
今回の3.11東日本大震災で、世界中から日本の良さや、その秩序正しさ、文化、精神性が称えられています。
そして、そんな日のいずる国、日本を助けようという感動のメッセージが世界各地から届いています。
私自身、極端な民族主義者ではありませんが、米国、韓国への留学経験や、仕事などで何十回という海外渡航の経験から、日本の文化や精神性の素晴らしさを身に染みて感じていますし、日本で生まれ育ったことを誇りに思っています。

「もののあわれ」
新しく生まれ来るもの、咲き誇って散っていくもの。
日々、同じようなことの繰り返しのように見えても、時は流れ、変化し、そして循環しています。
茶道に由来する「一期一会」という言葉も、こういう精神文化から出てきたのでしょう。
人との出会い、これもまた、もう二度と巡ってくることがないたった一度きりのものとして、今、最高のおもてなしをするという美学。
そういえば、「もののあわれ」、「無常観」という言葉で思い出す出来事があります。
私が幼い頃、とても大切なおもちゃを壊して、泣き叫んでいたときに、父から言われたことを今でも覚えています。
「形あるものはいつかは壊れる」
この言葉を聞いたのが、まだ小学校の低学年だったと思いますが、以来、私の一つの思考の種になっているような気がします。
目に見えるものばかりに執着するのではなく、目に見えない心(しん)の部分を見つめていかなければなと。。
昨日、昼食をとりに外に出たときに、やっとゆっくりと桜の花を愛でるチャンスがありました。
もうすでに満開は過ぎ、葉は伸び、花びらが散り始めていましたが、その頃の桜が一番好きです。
ここ数日で桜の花は散っていきますが、また来年の今頃、綺麗に咲き誇ることでしょう。
形あるものはいつかは変化し、また新しいものを生み出していく。
最も大切なものはみな、目に見えないところにある。
花びらが舞い散る桜の木の下で、そんなことを考えながら過ごしたひとときでした。